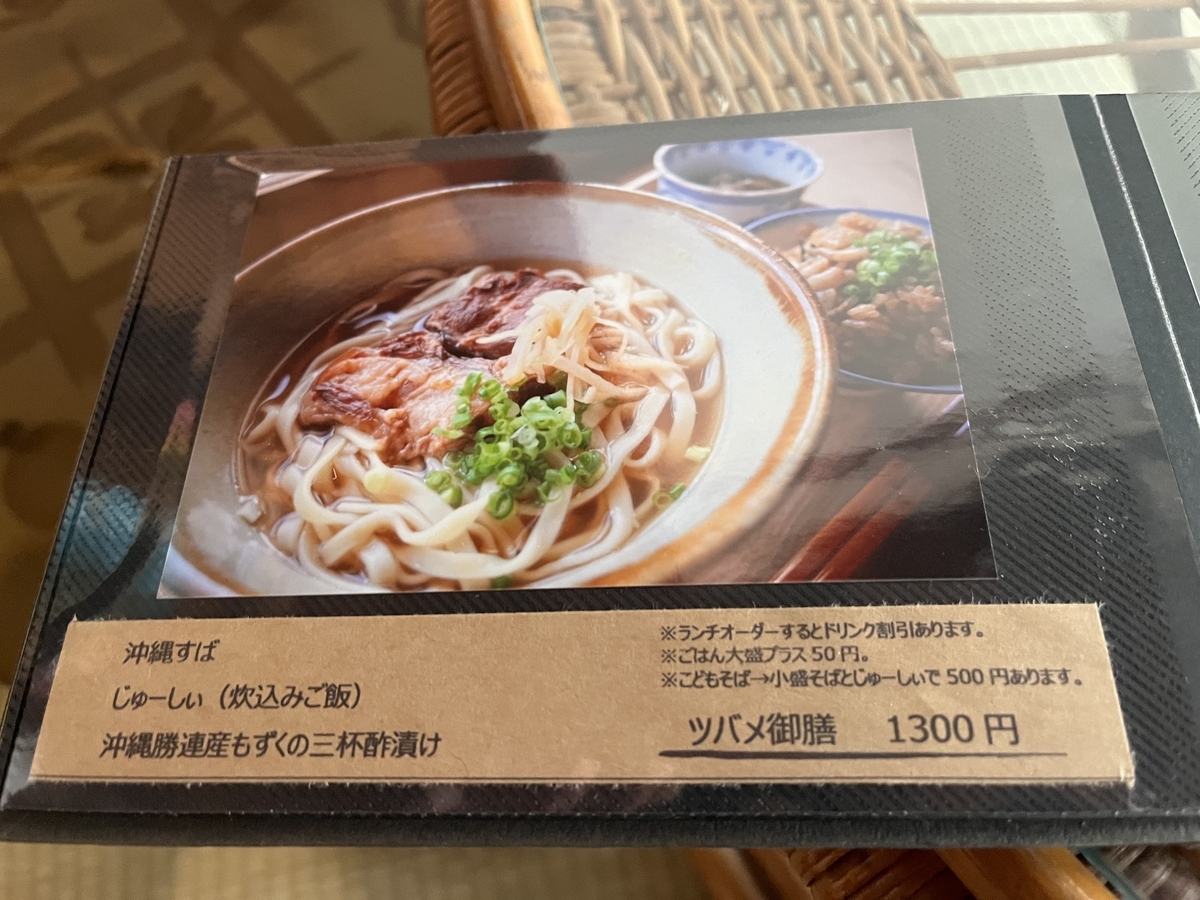こんばんは。TUBOSUGI1975です。
今回は1月下旬に奈良県吉野郡東吉野村の薊岳に冬登山してきましたので簡単に紹介したいと思います。
薊岳と登山ルート

薊岳は奈良県吉野郡東吉野村と川上村にまたがる標高1,406mの山で近畿百名山、奈良百遊山の一つに数えられています。
台高山脈主稜線から西側に派生する縦走可能な稜線上に位置しており、とても眺望の良い山です。
登山ルートはいくつかありますが、旧大又バス停近くの笹野神社からの登山ルートはあまり使用されていない感じで大又林道からP1334の稜線に出るルートか明神平から稜線に出て前山とP1334を経由するルートが一般的かと思います。
大又林道からP1334に出るルートはかなりの急登ですので、登りも下りも注意が必要です。
林道歩きが地味に疲れる

大又林道ゲート手前の駐車場までの道は現在、通行不可のため七滝八壺手前の駐車スペースらスタートです。

七滝八壺

本来ここの手前まで車で来れるのですが、現在は通行止めのため2キロ以上歩く必要があります。この林道歩きが往復5キロ近くあるので地味に疲れます(-_-;)

先ほどのゲートから少し進んだ先にP1334に向かう入山口があります。滝の横に鉄製の階段があるので分かりやすいかと思います。
P1334までの急登でクタクタ

かなりの急登が続きます。この日は積雪が多かったのでチェーンスパイク10を装着して登りました。

標高1,000m付近から霧氷が現れました。

真っ白

寒い・・・

P1334に到着しました。積雪のためいつもの倍近くの時間と体力を使いました。この時点でほぼ燃え尽きていました(笑)
薊岳の銀世界に酔いしれる

P1334から薊岳まではノートーレスの稜線歩きでした。

美しい霧氷が折れかけた心を励ましてくれます。

積雪が膝まであるのでなかなか進みませんでした。

神々しい雰囲気です(^^♪

薊岳に到着しました。

ガスで目線から下の眺望がありませんでした。

ちらっと大普賢岳
ノートーレスの尾根歩きに大苦戦

薊岳からP1334に戻り明神平に向かいます。

少しガスが晴れてきました。

霧氷

いつもは快適な稜線歩きですが積雪のため悪戦苦闘(;^ω^)

やっと前山に到着しました。
旧ゲレンデの明神平の景色に感動

前山からは明神平に下って行きます。

明神平はかつてスキー場だったことがよく分かります。久しぶりにスノボをしたくなりました♪

少しの時間ですがガスが晴れたので素晴らしい眺望が得られました。

来て良かったと心から感じます。

リフトの残骸

休憩ポイントに到着。帰りは一帯がガスの中でした。
おわりに

以上が雪の薊岳の簡単な紹介でした。
初めて積雪の薊岳に登りましたが想像していたよりも疲れました。大又林道から登った選択は正解だったと思いました。
明神平から前山を経由してP1334に出るルートは体力的には楽ですが、P1334から大又林道に下山するのは危険だと感じました。積雪の激下りは避けて良かったです。
しかしながらノートーレスの薊岳の雪景色は美しく大満足な山行となりました!
最後までお読みいただきありがとうございましたm(__)m